IR
セントラル硝子が目指す姿
構造改善に立脚した新中期経営計画
当社では、これまで低収益事業からの撤退による構造改善と、ポートフォリオの再構築による事業収益基盤の強化、財務基盤の強化を進めてまいりました。
まず、伝統的な基幹事業であるガラスセグメントにおいては、2007年から赤字が続いたことから、事業撤退、需要に見合った生産能力の削減等による収益改善施策を実施してきましたが、2022年に最大の赤字部門だった海外自動車ガラス事業からの撤退を完了し、国内での新しい体制の構築により安定的な黒字体質への転換を図りました。また、もう一つのガラスセグメント事業であるガラス繊維事業については、自動車市場での生産台数の減少の逆風を受けましたが、当社の強みを活かせる製品ラインアップに注力することで、利益を堅持しています。こうした構造改善をしながら、全体の事業ポートフォリオを整備しました。化成品セグメントの医療化学品、エネルギー材料、電子材料を3本の柱として考え、新たな価値やビジネスモデルの創造を図る「スペシャリティ製品」の創出を研究開発の中心と位置付けました。その一方、収益の基盤となる安定的な基幹製品を「エッセンシャル製品」と位置付け、「スペシャリティ製品」と「エッセンシャル製品」の両輪で進めることをポイントとしました。
この方針のもと、2022年度・23年度は好業績を収めました。ところが、2024年度になって伸び続けていた電解液のEV(電気自動車)需要が様々な要因で減少したため、エネルギー材料事業は利益ベースで50億円程度大きく下振れ、赤字に転落しました。
その結果、前中計最終年度2024年度の実績は、財務目標である営業利益140億円、ROE12%に対し、利益、ROEとも未達となりました。ただし、2022年度、2023年度において、エネルギー材料事業、電子材料事業をはじめ、化成品セグメントの堅調な需要を取り込み、営業利益140億円を2年連続で達成しております。また前中計3年間と、その前の3年間を比較すると、2倍以上の営業利益を獲得できています。これは、ガラスセグメントの構造改善を含め、ポートフォリオを大きく見直した成果です。
当社は、社会・市場の動向により業績が低迷した後、短期間のうちにV字回復を遂げてきた実績があります。新型コロナでも、リーマンショックでもそうでした。独自の研究開発により新たなシーズを常に温めていることで、次の収益源となるビジネスがスムーズに軌道に乗り、V字回復につながっていると考えています。

新中計は2段階に分け、「VISION 2030」の実現を目指す
2025年度より「VISION 2030」の達成年度を含む新中期経営計画をスタートさせました。当社のありたい姿は、「サステナブルな社会の実現に寄与するスペシャリティ・マテリアルズ・カンパニーになる」です。ありたい姿に対して、『人的資本経営の推進』『環境課題の対応』『デジタル活用の推進』によって事業基盤を強化しながら、「スペシャリティ製品の拡大」と「エッセンシャル製品の強化」の2本柱の事業戦略に取組むことにより、2030年度の数値目標として過去最高益である「営業利益200億円」と「ROE 10%以上」を掲げました。その達成への道筋が新中計の骨子になります。
新中計は、Phase1・Phase2の2段階に分かれています。Phase1は2025〜2027年度にあたり、「未来に学んで、高みへ挑んで、力を育む」時期です。ここでは成長への基盤を固め強化します。その後の2028〜2030年度がPhase2で、「挑戦が拓く躍動のステージ」ということで利益をしっかり数字として表し、VISION 2030の目標である営業利益200億円の実現を目指します。
こうした数字を含む情報開示を充実させるため、事業の開示セグメントを変更しました。これまで「化成品事業」と「ガラス事業」の2つでしたが、新中計初年度の2025年度から、従来の化成品事業を「電子材料」「エネルギー材料」「ライフ&ヘルスケア」の3つのセグメントに分け、5つのセグメントで開示を⾏っていきます。
今回の新中計の大きなポイントであり、Phase1の肝にあたるのが、EV需要の減少で不調に陥った電解液事業の回復、そして先の成長(投資戦略)を目指す取組です。やるべきことは3つあります。
1つ目は、電解液事業において非常に重要な、将来的にも有望で、強い立ち位置を持っているお客様を獲得することです。現在でも、世界的にも優れた企業を顧客としており、その取引をさらに伸ばしていきます。2つ目は、中国でのエネルギー材料事業の拡大です。当初は中国電解液市場への直接参入をしたのですが、競合が乱立する状況において、なかなか折り合いがつかないポイントがありました。それなら、私たちの技術を使ってもらおうと、ライセンス提供に舵を切りました。私たちの優位性がある技術は、きちんと認められた上で、すでに複数社と契約を結んでいます。中国企業はヨーロッパでも優勢で、彼らを通してヨーロッパ市場にアプローチができると考えています。
このように、すでにいくつかの手は打ってあり、EV市場の回復とともにエネルギー材料事業はV字回復への道筋が出来上がりつつあります。2026年度に⿊字転換させ、2027年度には営業利益30億円を稼ぐまで持ち上げる計画です。

次代の収益の種に積極的に投資する
3つ目は、投資戦略です。経営資源をメリハリつけて配分する戦略を積極的に実施し、Phase1では「成⻑への基盤強化」を、Phase2では「本格的な成⻑軌道へ」を実現してまいります。
成⻑軌道への道筋をしっかりとお示しするため、新中計ではROICマネジメントを採用しました。ROIC(Return On Invested Capital)は、投下した資本に対してどれだけの利益を生み出しているかを測る財務指標です。Phase1ではROIC 6.1%、Phase2ではROICを7%と設定しています。
新中計の投資戦略は、成長事業への投資、中でも電子材料の半導体向け製品が筆頭になります。当社は、資本市場で半導体関連株のカテゴリには位置付けられていませんが、現実的には半導体向け製品の利益貢献の規模は大きく、これからもっと半導体向け製品群が当社を牽引する流れになります。ますますダウンサイズ化する半導体の素材や材料に関わる研究開発や、電力損失を大幅に低減するため、省エネルギー化のキーデバイスとしてSiCパワー半導体が注目される中、当社の新中計におけるPhase1・Phase2の合計投資額は1,000億円超で、そのうち電子材料分野を含む成長投資に370億円を投じVISION 2030を達成する基にします。
電子材料分野以外ではノンプラスチックの被覆肥料の開発に注力してまいります。現在、お米の問題が深刻化しています。農家の高齢化、農業の担い手不足がありお米を作付けする田んぼがどんどん減っています。当社は、日本の食料安全保障としてお米は非常に重要だと考えており、きちんとこのような農業環境に合った、農家の生産性を上げるための省力肥料を提供していきたい、また、一方でマイクロプラスチック問題を解決する環境に配慮したサステナブルな肥料を提供したいと考えています。そういうことでプラスチックを使わないノンプラスチックのコーティング肥料を開発し、これから立ち上げていきます。今年から田んぼでの実試験を始め数年かけてボリュームゾーンになるような規模で投資を行います。
また、ライフサイエンスの入り口となる細胞シートと呼ばれる製品など、次代の主要な収益の種を今、蒔いているところです。研究開発は当社のものづくりの中核であり、将来の事業の重要なモチベーションとして、幅広いシーズへの投資を展開していきます。

サステナビリティは当社の経営基盤そのもの
パーパス(存在意義)にサステナブルな社会への貢献を謳っている当社にとって、ESG経営は事業を支える経営基盤そのものと言えます。
環境課題については、カーボンネガティブな素材開発や、フッ素廃棄物の再利用、太陽光電池パネルのガラスの再生利用など、環境対応製品・技術の開発と実用化に取組んでいます。CO2のクレジット取引にとどまらず、実際にCO2の排出を減らす技術や製品が不可欠だと思います。当社の技術は、こうした現実的な地球環境の保全に貢献できると考えています。
当社は、2030年の GHG※削減目標を2022年に前倒しで達成するなど環境課題に対し真摯に向き合ってきましたが、2023年に社内のサステナビリティ委員会などでの議論を経て、環境保全への対応を含むマテリアリティを策定し課題解決に取組んでいます。今回、新中計の策定に合わせ改めて環境負荷低減のマテリアリティを設定し取組を推進していきます。
DXも推進し、新中計期間にはさらなるDXへの投資を拡大する計画です。労働人口減少に伴う人材不足に対応するための業務の効率化と生産性向上、データの正確性と信頼性の確保にDXへの取組は不可欠です。すでに基幹システムERPの刷新を進めており、これを足掛かりにDXへの環境整備を進めてまいります。Phase1・2の累計で100億円以上のデジタル関連投資を計画しており、投資対効果として2030年度には20億円の増益を目指しています。
ガバナンスも強化します。先般の定時株主総会で監査等委員会設置会社に移行しました。取締役会の役割をよりモニタリングに寄せて、業務執行側でスピーディに動き、その執行内容や結果は取締役会に報告しますが、取締役会では中長期的な企業価値向上に資する議論をしていきます。今までの監査役会設置会社は、取締役会が最終決定機関であり、意思決定までに非常に時間がかかっていました。そこを短縮しつつも、しっかりと監督してもらうという立ち位置に変えました。また、社外取締役の比率も全体で60%と過半数とし、より一層ガバナンスを強化しています。また、2人の女性取締役を起用することで、女性比率も20%を達成しました。
- GHG:温室効果ガス

働くことの嬉しい職場環境を目指す
ここまでお伝えした計画や戦略を実行するのは、一人ひとりの社員です。当社は、人材こそ最大の経営資源であり、成長のキードライバーと考え、「ひと」の活躍を支え、企業価値を高め続ける人的資本経営を推進します。人材の価値を最大限引き出せるように、また社員のやりがい、モチベーション、満足度を高めるために、「人材育成強化」「従業員エンゲージメント向上」「働き方と労働環境の整備」など、5つのテーマで人的資本への投資を拡大していきます。
人的資本経営で私たちが目指すのは、「働くことの嬉しい会社」です。社員一人ひとりが自分の目標や使命感を持ってがんばれる。会社に来たいと思う。そんな職場環境を整えたいと思い、社員との直接対話を進めながら、オフィスの移転や工場内の建物の建替えを行っています。ERPの刷新、DX推進で業務のあり方をより効率的に変え、組織を強靭化していきたいと考えています。働く環境を改善し、ものづくりの志を共有することで、経営層と社員の関係を、親しく、近しくしたいのです。経営幹部も現場の社員も、やりたいことにチャレンジできる。それぞれの立場で仕事の成果を目の当たりにして、働くことが嬉しくなる。明日はもっとがんばろうと思う。そんな会社を目指します。
人的資本経営推進に向けた取組

みんながワクワクする会社をつくりたい

当社は、素材・技術をベースとした研究開発型企業であり、化学の力でこの世界にまだないものを創るのが仕事です。自分の発想をゼロから形にできる、世の中に対して「こんなのはどうだ」と研究開発成果をプレゼンテーションできる、とてもワクワクする仕事であり、そのワクワクが業績や企業価値の向上にもつながっていきます。
そんなワクワクする気持ちを、社員や投資家をはじめとするステークホルダーの皆様に伝え、共有していきたいと思います。今後も統合報告書や経営概況説明会、ウェブサイト等を通して、ステークホルダーの皆様に必要な情報をタイムリーに発信していきます。皆様と情報を共有し、皆様との対話を経営に反映することで、社員も、取引先も、投資家も、みんながワクワクを分かち合える会社をつくってまいります。
- 本メッセージは2025年9月発行の統合報告書トップメッセージより転載しています。
代表取締役 社長執行役員
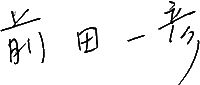
Contact
お問い合わせ
ご回答は月曜日~金曜日(祝日および年末年始を除く)の弊社営業時間にご連絡いたします。
また、お問い合わせの内容によってはご返答いたしかねる場合もございますので、予めご了承ください。

